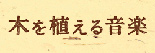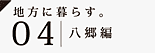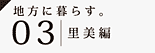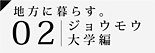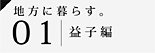[地方に暮らす。[八郷編]] 記事数:7
| 前の記事 >
|第五話|八郷は大事なふるさとだから
筑波山を望む八郷地区。瓦屋根の家並みと、広がる田園。日本の原風景を思わせる、自然豊かな場所です。温暖な気候で昔から稲作などの農業が盛んだった八郷地区は、有機農業の郷としても知られ、地元農協では、毎年、有機農業を志す新規就農者を受け入れています。
鶏を飼い、冬の間、落葉する里山の落ち葉をさらい、堆肥を作り、育てる野菜で季節を感じることのできる場所。自然の循環とともにある、土に近い暮らしが、脈々と続いています。
戦後、高度経済成長時の昭和40年代は、養豚、葉タバコ栽培、養蚕などの換金作物(※自給用ではなく、売ることを目的に作る農作物)の栽培に特化する流れがあり、効率化を目指し化学肥料などを使用する農業のやり方が、この辺りでも主流でした。しかし、昭和50年代に入ると、農協を挙げて「地域の新しい農業のやり方」を模索するようになりました。都市部の生協との地域総合産直運動や有機野菜を入れたグリーンボックスという商品づくりなどがその一例です。JAやさとに有機部会ができて、20年近くがたっています。当時、農協が有機農業の支援を始めたというのは全国的に見ても特筆することで、八郷にいる「地の人」の存在なしには、実現困難なことでした。
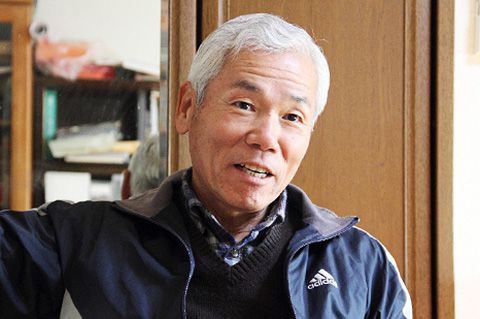
そのキーパーソンが、現在、廃校になった小学校で農業体験などの事業を行う「NPOアグリやさと」の代表、柴山進さん。元JAやさとの職員で、農協人文化賞を受賞しています。柴山さんは、1951(昭和26)年生まれの現在63歳。東京や千葉の中学生の農体験の受け入れや、親子の食農体験を生協と一緒に企画しています。
■
朝日里山学校がやっていること

朝日里山学校は、旧朝日小学校が廃校になった4年後の平成16年に、体験型観光施設として市が運営を始めました。農協を定年退職した柴山さんが立ち上げたNPO法人に、運営を任されて5年がたちます。現在は、田植えや芋掘りなどの農業体験をはじめ、そば打ちやピザ焼き体験など、農と食の体験を中心に、里山の暮らしを体験できる場所として、県内はもとより首都圏からも来校者があり、その数は年間で延べ1万人を超えます。


―ここまで人を集められるようになるまでには、どんなことがあったのでしょうか?
柴山:もともとは、農協で、生協の組合員向けに親子の農業体験の受け入れをしていました。最初の受け入れは、平成元年の頃だったかな。JAやさとの野菜を産直(産地直送)していた(東京の)東都生協さんに、親子の農業体験の受け入れを依頼されて、最初は1反2畝の田んぼで100人からスタートしました。でも最初は着替えをする場所もなくてね。平成11年に東京の学校の子どもたちの受け入れも始まると、だんだん拠点となる場所が必要になってきて、場所を探していたところに、この朝日里山学校の運営を任されたんです。
―グリーンツーリズムという言葉が提唱されはじめた平成の初頭にいち早く、柴山さんは農村での体験プログラムづくりに取り組み始めました。
柴山:もう20年以上がたつけど、印象的なことは本当にたくさんあります。中でも、千葉の中学校の子どもたちに、食べ物と農業について話をしたときのことは特に印象に残っています。田植えをして、みんなでお昼を食べた後、命をいただくということを話したら、ぼくが会場を出るときに、駆け寄ってきた女子生徒に握手を求められて。そのときに「あぁ伝わったかな、何か感じてくれたかな」と思えて、うれしかったね。
今じゃ、20年前に来た子が、その子どもを連れて来てくれているんだよ。八郷は大事なふるさとだからと言って来てくれている。こんなにうれしいことはないよね。
■
JAやさとの産直の取り組み
―農協職員時代のつながりを、今でも大切に、そして今なお、広げている柴山さん。でも、そもそも、農協が都市住民の農業体験を受け入れるようになったきっかけは何だったのでしょう?
柴山:きっかけ?それは話すと長くなるよ(笑)。でも時代の流れと、タイミング、そしてそのチャンスを生かせる組織の体制が全て整っていたということに尽きるような気がします。順を追って、説明していくと、農協で産直を始めて、都市の消費者とのつながりができたのが、最初のきっかけです。
1980年の半ば、ぼくが30代の半ばだった頃。当時の生協は、会員を増やして、すごく伸びている時期で、その伸びを考えると、生協は、地域の農協と手を組んで産直を始めないと、生産が間に合わないといって、一緒にやってくれる地域を探していました。
同じ時期、八郷では、葉タバコ農家が次々と辞め始めていって、次の新しい農業の方法を探していたところでした。当時の組合長は「山を大切にする」という考え方の人。「山を大切にする」というのは、つまり自然を大切にするという意味なんだけど。組合長は、常に次の時代を見通している人だったから、生協の「地域総合産直」という考え方に賛同して、農協を挙げて、地域総合産直に取り組もうということになりました。
※地域総合産直には、「未来の子どもたちに残したい、安心して暮らせる食糧生産の拠点を守る」という考え方が根底にあります。例えば、卵を1万個欲しいという都市の要求に応えようとすると、過剰な鶏の糞が、地域内で処理しきれなくなり、その土地の土のバランスが崩れてしまいます。「これだけ欲しい」という要求に応えようとすると、その結果、地域がつぶれてしまうのです。そこで、卵だけでなく多品種の野菜を栽培し、それを個々の生産者がそれぞれに取り組むのではなく、地域的な広がりをもたせていくことで、「永続的な農業を行える地域にしていく」という考え方の実践が、地域総合産直の運動でした。
柴山:タイミングのよいことに、産直を始めた1986年は、地元の農家の人たちが作った野菜をまとめて受け入れられる農協の中央集荷場ができたところ。最初は、もともと栽培している、絹さややインゲンなどから始まって、翌年の87年には、“こういうものを栽培してくれ”という依頼がくるようになった。それで、組合員に例えば“小松菜、チンゲンサイ、大根を作ってください”と声を掛け始めるようになりました。
―地域総合産直という考え方に対して、当時の地元の農家の皆さんの反応はどうだったのでしょうか?
柴山:賛同してくれましたよ。最初のスタートは20人くらいからだったかな。でも八郷はもともと野菜の生産地じゃないから、そこまで技術を持っている人がいなかったんです。だから、当時は職員が種苗会社に泊まり込みで野菜づくりを勉強しに行き、地元農家の方に技術指導ができるように、取り組んでいました。とにかく、何もかもが初めてのことばかり。生協産直は、栽培だけでなくて、出荷の仕方や支払いの方法などの仕組みづくりも新たに考える必要がありました。例えば、生協に出す野菜、市場に出す野菜という具合に出荷先を分けてもらうようにお願いしたり、市場と生協分をプールする品目を決めたり、それを別々に精算する仕組みを作ったりと、公平にお金を分配することを考えました。
葉タバコ、養豚、養蚕、米、果樹などに特化していた八郷の農業が、多品種の野菜栽培に切り替わっていったのはこの頃かな。みんな、毎年、新しい種類の野菜づくりに挑戦していて、86、87、88年の出荷量の伸び率はすごかったですよ。
―地元の人が参加しやすく、そして、がんばった人が報われる産直。言葉で理念を伝えるのは簡単ですが、柴山さんは、その仕組みを実際に作り、運営していく上での壁を乗り越えてきました。ある時は、言葉にして伝え、ある時は、行動で見せる。当時を振り返って、柴山さんは「栽培品目が増えていくというのは、生産者の所得が上がっていくということ。だから仕事をやっていて楽しかったなあ」と話します。
■
産直の取り組みから、有機部会・新規就農者を受け入れるまで
―80年代、右肩上がりだった農協の産直の流れが、現在の八郷を形作ってきました。八郷の農業は、時代の求めに応じて、順調に成長してきたということでしょうか。
柴山:いい流れはずっとあったけど、もちろんピンチもありました。バブルが弾けた頃、生協の組合員さんは都市部の人が多かったから、その影響を受けて、売り上げが止まってしまった時期があったんです。そんなときに、東都生協の風間さんが、一緒に八郷の地域総合産直の商品を作ろうと言ってくれて、95年に7品目の入った野菜セット(グリーンボックス)を始めました。珍しさもあって、1年目は4900の登録があったんだけど、次のシーズンは3500、その次は2500というように、段々登録者が減っていくようになったんです。その原因は、セット野菜に欲しくない野菜が入っていたり、食べきれないうちにまた来ちゃったりというものなど。このままでは大切なグリーンボックスがなくなってしまうと思い、1品でもよいから有機栽培の野菜を入れようと考えてできたのが、JAやさとの有機部会です。97年のことでした。
このころ仕事で月に4回以上、東京に行っていたんですが、東京の人とよく話をするようになると、都会の人が何を求めているのかが分かってきたんです。当時、八郷では農業をやめる人がどんどん出てきていましたが、逆に東京では、農業に興味を持つ人がいるというのを肌で感じていました。有機部会もできていたことで、新しく来た人を受け入れる受け皿もあったので、東京で働いている人から農業をやりたいんだという相談を受けるようになると、彼らを受け入れる体制づくりを始めました。
それで、できたのが「ゆめファーム(http://www.jayasato-yuukibukai.com/kensyu.html)」。農場と農機具など必要な支援を受けながら、2年かけて、栽培から農協を通した販売までを学んでもらう制度です。さっそく相談してくれた人が、このゆめファームの第1期生として、家族でやってきてくれました。研修期間は2年だから、とりあえず、2年が終わったら別の人を探そうと思っていたところに、次の年、小さい子どもたちのために、農業をやりたいと相談にくる人がいて。1家族入ると1家族出るという仕組みで、1999年から始まって、これまでにもう17組の家族を受け入れています。
■
地域農家の支援、新規就農者の受け入れを経て、今思うこと・柴山さんのふるさとに対する思い

―今、地方への関心が高まり、その可能性や必要性を見出す人も増えてきていると思います。農業を志す人を受け入れ、20年近く、地域とつなぐ活動をしてこられた柴山さんは、これまでの経験を踏まえて、今どんなことを感じていますか?
柴山:2001年9・11のテロやBSE発生以降、時代が大きく変わってきたなと感じます。世界の仕組みを壊したのがテロだとすれば、食糧流通の仕組みを壊したのがBSE。これまで、外国産の豚肉ばかりで、海外でBSEが起こったからといって、すぐに、国産の豚肉や鶏肉の生産が間に合うわけがないのに、国産のものを求められるから、起きたのが産地偽装事件。
安ければ安い方がいいという価値観だけだと、生産者だけじゃなくて、結局、消費者も、自分たちの首を絞めることになってしまいます。でも価格での競争という面も確かにあるのが事実で、そんな悩みの中にありながら、良いものを提供するために、農業を続けている生産者が、八郷にはたくさんいます。
―八郷という地域と、そこで農業を営む人たちの未来を考えたときに、これからは、多品目栽培であり、有機栽培だと考え、ゼロから仕組みを作り上げてきた柴山さん。土日も関係なく仕事をしていたころ、久しぶりにキャッチボールをした息子さんに、「お父さん、今日は、家にいて遊んでくれるんだね」とうれしそうに言われた言葉が忘れられないといいます。柴山さんの仕事に対する思いは、どこから来るのでしょうか。
柴山:実家は、農業で食べていけるような面積もない小さい農家だったけど、高校を卒業したら、すぐに農業をやろうと思っていました。それで、農業大学校に行ったんだけど、半年でやめて、JAやさとに勤め始めることに。ここに生まれたし、長男だったから、地元の人に仕えることが一番いいと思ったんです。
今まで、仕事をしてきて壁にぶつかることもあったけど、どうしたらできるんだろうという考えばかりで、目の前のことに一生懸命に取り組んで、ちょっとずつ階段を上がってきたように思います。これは、本当の話なんだけど、ぼくは、今まで、ストレスって感じたことないの。ストレスって分からないんだよ(笑)。
先を見通してリーダーシップを取ってくれるトップがいて、ひと声かければ、同じ方向を見れる仲間がいたから、やりたいことがやってこれた。ない仕事をつくっていく“しごと”、形にしていく“しごと”。こんなに楽しいことはなかったですね。
今の若い人たちは大変だと思う。あるものを維持していくのも、大変だから。でも、どんどん外部に出ていって、いろんな人と接して、自分の幅を広げていってほしいと思う。上から言われて仕事をするような場所じゃない。どんどん出ていって勉強していってほしい。そういう若い人が出てきてほしいと思っています。

―最後に、柴山さんに、八郷の風景のどこが好きですかと尋ねると、「山と畑とバランスがちょうどいいところ」という答えが返ってきました。この風景は、しかし、当たり前にあるものではなく、地元の農家の方たちが手をかけてつくってきたもの。柴山さんのお話を聞いて、ちょうどいい風景には、情熱を傾けた記憶や、仲間たちとの思い出がたくさん込められていたことを知りました。八郷の風景には、そこで暮らし働いた人の存在が溶け込んでいます。(Maki Takahashi)
[地方に暮らす。[八郷編]] 記事数:7
| 前の記事 >
「ゆたり」は時の広告社の登録商標です。
(登録第5290824号)