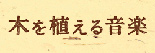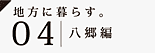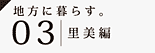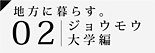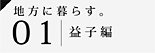第一話〜第十九話はゆたり出版の「かさまのうつわ」に再編集し収録されています。「かさまのうつわ」はネット通販、書店、販売協力店でお買い求めできます。詳しくは本とゆたりをご覧ください。
第十七回 戸田浩二さん

陶芸家になる道は人それぞれ、千差万別ではあるけれど、実業団のスポーツ選手が陶芸家に転向したという例を、私は他に聞いたことがありません。笠間に2002年に築窯した戸田さんがその人でした。
1974年、愛媛に生まれた戸田さんは、中学生でサッカーを始め、高校までを過ごします。「大学は、サッカー雑誌で当時日本一を獲っていた筑波大の特集を見て、筑波大を目指しました。ポジションはディフェンス。その頃の筑波大にはすごい選手ばかりが集まっていたんです。その中でひたすらサッカーをする毎日でした」

筑波大学体育学群を卒業した戸田さんは、プリマハムFC土浦(現在の水戸ホーリーホックの始祖の一つ)に入団します。実業団の選手として午前中は会社で働き、午後は練習。週末ごとに試合がある、やはりサッカー一色の生活を1年続けた頃、戸田さんはサッカー選手としての自分に限界を感じたと言います。「自分はこれ以上ここにいても、先が見えていると思いました。入団1年でサッカーをやめ、愛媛には帰らず福島のペンションで住み込みのアルバイトを始めました。雪かきをしたりしながら、これからどうしようか考えていたのですが、そこでペンションの人に、蕎麦屋かカメラマンか陶芸家の知り合いがいる。興味があるなら紹介する。と言われたんです。それまでサッカーばかりで見たこともなかったのに、三つの中でなぜか陶芸という言葉に魅かれました」。その後アルバイトをやめたため、福島で陶芸をする機会はありませんでしたが、戸田さんが次の行先として選んだのが笠間でした。

「当時355号沿いを歩くと、今よりたくさんの焼き物屋さんがありました。いろいろな作品を見て、陶芸は個人の名前で仕事ができるところがいいなと感じたんです。弟子のような形で勉強させてくれるところはないか聞いて回ったのですがそのときは見つけられず、仲田製陶所で1年間勉強させてもらいながら弟子入り先を探しました」。1年後、伊藤東彦氏に師事。4年を過ごします。
「先生が薪窯を作るということで一緒にやらせていただき、薪窯の面白さを知りました。また、個人として作品を発表していく取り組み方、考え方を学んだ4年間でした」
サッカーから陶芸。がらりと世界が変わった独立前の5年間はどんな月日だったのでしょう。
「陶芸を手取り足取り習うというこいうことはなく、日中は先生が制作をするのにどんな流れを作ったらいいのか考えながらアシスタントをし、夕方それが終わってからがろくろに向かえる時間でした。この期間は当然自分の名前で作品を発表するということもなく、毎日は楽しかったですが悶々とすることもありましたね。本屋に行ってサッカー雑誌を手に取ると、少し前まで一緒にやっていた先輩や仲間が活躍している様子が載っていたりして、それは随分刺激になりました。サッカーに戻りたいという気持ち? それは、まったくありませんでしたね」

目の前でお話しくださる戸田さんは、私が勝手に抱いていたスポーツ選手のイメージから遠くかけ離れた、静かで淡々とした雰囲気の方。サッカーというと少なからず「動」の熱気を想像していたのですが、ご本人も、そして作品も「静」そのもの。
「陶芸とサッカーに共通点があるとしたら、反復して身に付けていくということでしょうか。ろくろにしてもサッカーの技術にしても、繰り返すことで体に染み込ませていきますから」
アトリエには、見ていると思わず背筋が伸びるような緊張感をはらんだフォルムの花器などが並びます。
「土は自分で高萩や桜川から採ってきたものだけを使います。陶芸は素材がとても大事ですね。こうして採土できるのは、笠間という産地の強みだと思います。堤綾子さんや黒田隆さんら先輩たちが、40年ほど前に使える土があることを見つけて採土する道筋をつけてくれました。先輩がいろんなことをやってくださっていることも、産地ならではと感じます」
現在は銀座のギャラリーで作品が展示販売されており、2014年にはニューヨークで個展を開催しました。
初めて土を触ってから15年ほど。熟練と精神性を感じさせる造形はどのようにして戸田さんのものになったのでしょうか。
「伊藤先生の“いいものを見なさい”という言葉に影響を受けました。ここから東京は日帰りで行けるので、美術館に行っていろいろ見ていると、その中に自分の中に引っ掛かってくるものがある。須恵器や中国の古い青銅器だとか。そういうものが、今自分がやっている焼き物の元になっていると思います」
お話を伺いながらいただいたお茶の碗もご自作。唇をつけた途端、その薄さに目の覚める思いでした。「こういう薄さも、日常使いのものではないと思うんです。でも僕はあえてそういう物を作っていきたい。水瓶にしても、何かこう“捧げる”ものを。家の中に、そこに行くと気持ちが鎮まるようなハレの場が一カ所くらいあってもいいと思うんです。そういうところに置かれる、祭器のようなものを作っていきたいんです」
★
たち公子さん

戸田さんの焼き締め水瓶(すいびょう)を携えて向かったのは、たち公子さんのお宅。ご主人の圭祐さんは、笠間で本業の鈑金塗装業の傍ら「花屋台カフェ」の名で移動カフェを営んでおり、コーヒーの美味しさに定評があります。
花屋台カフェがオープンするときカウンターにいつもあるのが、公子さんの生けた花。広々とした庭一面で育てている植物を摘み、花屋台カフェのために生ける。そのかれんな花の風情に目を奪われ、コーヒーを待つ行列の時間も心楽しくさせてくれるのです。
「花がないと、営業の形が決まらない」と圭祐さん。「花屋台と言う名前は季節の花と僕のコーヒー屋台のことなので、花はなくてはならないんです」
茨城県筑西市生まれの公子さんがお花を始めたのは20代初めの頃。10年間通った草月流では師範の資格を持ち、後半同時期に東京の青山にある教室でフラワーアレンジメントを6年ほど学びます。
この日、テーブルに公子さんが用意してくださった草花は、すべてご自分の庭から集めてきたもの。「お花は、買うということはほとんどないですね。その季節にあるものを採ってきて生けることが多いですね」。こういう取材には慣れていなくて…と、恥ずかしそうにほほ笑みながら、言葉少なに花を扱う、その手つきの優しさに、つい見とれてしまいます。
「お花を生けていると、無心になれるのがとてもいい」という公子さんに、戸田さんの器の印象をお聞きしました。
「色も形も、とても品があると思います。凛としていてそこもすてきですね。形が完璧なので、お花は一輪挿すだけで他に入れる必要がないかな、とも思うのですが…。いつもはカジュアルなガラスベースなどを使っているので、今日はちょっと緊張します(笑)」
話しながらも手を止めることなく、ほとんど迷いなく生けたお花。
「今(2月)は庭にあまり花がないのですが、それを集めてこれから来る春を表現できたらと思いました」

焼き締めの水瓶に、まるで優しい春が宿ったよう。花を受け止める戸田さんの器も緊張感はそのままでありながら、ぐっと親しい表情を見せてくれます。どこか仏像の肌合いを思わせる高貴な水瓶。初めは触ることすら少し怖いように感じていたのですが、花を頂いた器を眺めるうちに、その「良さ」がすっと伝わって、焼き物はまさに手に触れて使える美術品なんだと実感しました。(しばた あきこ)
DATA:
花屋台カフェ
不定期営業。出店場所、時間等はtwitterでご確認ください。
HP|http://twitter.com/hanayatai/
「ゆたり」は時の広告社の登録商標です。
(登録第5290824号)