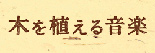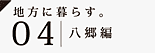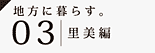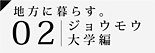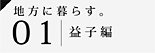「ひとが輝くまちの学校」はゆたり出版の「ゆたり文庫 地方に暮らす。シリーズ02 ひとが輝くまちの学校」に再編集し収録されています。書籍はネット通販、書店、販売協力店でお買い求めできます。詳しくは本とゆたりをご覧ください。
|第六話|街に眠るものづくり
「ものづくり」という言葉に感じる親しみと比べ、つくり手や製作の現場はどうでしょう。少し特別で遠い存在に感じられないでしょうか? 今回は、ジョウモウ大学の授業が行われた群馬の企業とそのものづくりについて、いくつかご紹介したいと思います。体験する機会だけでなく「こんな会社が群馬にあったんだ!」授業にはいつも驚きがあり、街に眠る魅力を発見する楽しさも伝えています。

■
住宅街にある、明治30年からつづく伝統工芸
「どうしてなのかな…」と難しい顏で首をひねるのは、創業明治30年、注染(ちゅうせん)という昔ながらの技法を守り、日本手ぬぐいをつくり続ける、中村染工場の四代目・中村純也さんです。昨年こちらで行われた授業への応募数は、募集定員の約5倍にもなり、いまだその記録は破られていないそうです。その理由を尋ねると、
「いや、授業の後も抽選に外れて残念だったって声をかけられることがあるんだけど、どうしてあんなにたくさん応募してくれたのか…」あまりの反響の大きさに、いまでも戸惑っているのだと、中村さんは難しい表情になってしまったのでした。
注染とは、型彫師がつくる手彫りの型紙をもとに、布に染料を注ぎ、染めていく、昔ながらの型染めの技法です。図柄や複数の色を染め分けるためには、防染糊(ぼうせんのり)という海藻でつくられた糊を用います。仕上がりまでいくつもの行程があり、技術はもちろんですが、勘に頼るところも多いため、長く修行を積まなければ一人前の職人にはなれないのだと、中村さんは教えてくれました。
染め上がった手ぬぐいは、外の干し台に広げられていきます。風に吹かれ自由に踊り出すと、染められた色柄が、わっと目に飛び込んできました。近頃、機械プリントの手ぬぐいも見かけますが、実は表地(片面)だけにしか柄がないことにお気づきでしょうか。注染では、表と裏の両面から、糸そのものをしっかり染めるため、どちらにも柄が入ります。
機械プリントと比べると、丁寧な仕事は一目瞭然。決して手を抜かない、職人気質のこだわりがうかがえます。しかし、残念ながら多くの伝統工芸が同じような状況にあるように、機械化の波は注染を営む工房を全国的に減らし、群馬県では、こちらが唯一の工房となってしまっているのです。


写真提供:ジョウモウ大学

■
世界に日本の伝統を伝え、日本の伝統に新しい風を

かつてお土産の定番として人気があった、こけし。子供の頃、おばあちゃんの家へ遊びに行くと、ズラリ並んでいたことを思い出します。いま、そのこけしのイメージは大きく変わってきているようです。群馬県榛東村にある卯三郎こけし。こちらで行われた授業に参加したのは、9割が、若い女性たちでした。講師をつとめたのはプロダクトデザイナーの手島彰さん。プロダクトデザイナーの考え方を学び、コンセプトを深く考えるところから、こけしの絵付けに取り組む授業が行われました。
こけしは大きく分けると、素朴さが魅力の東北地方に伝わる伝統こけし、型にとらわれない自由な姿かたちが特徴の創作(近代)こけしに分かれます。そしてこの創作こけしの生産量日本一が、群馬県です。卯三郎こけしでは、資材となるミズキやケヤキなどの原木の製材から絵付けまでを、自社の職人さんの手で担っています。
初代卯三郎さんは、こけしづくりに新しい技法を多く取り入れた先進的な職人さんだったそうです。現在は、代々受け継いできた創作こけしを守りながら、その技を活かした現代的なこけしづくりにも取り組み、若い女性の人気を集めています。
この新しいこけしづくりを始めたのは、三代目の岡本義弘さんです。お話を聞いて驚いたのは、こけしは日本的なイメージから海外でとても人気があり、特にアメリカやヨーロッパでは、安定して日本より高い需要があるのだそうです。そしてこのことが、岡本さんを新しいこけしづくりへと動かすことに。
「海外の人に喜んでもらえるのは嬉しいことですが、でも、日本の人に欲しいと思ってもらえるこけしをつくらなくて本当にいいのかって、ずっと疑問に感じていたんです」その想いから、現代のインテリアに溶け込むこけしや、キャラクターとコラボレーションするなど、これまでにない創作こけしが生まれたのだそうです。昭和のおばあちゃんたちを魅了したこけしは、新しい魅力をまとって、日本の伝統工芸に新しい風を呼び込んでいます。
※写真(上)こけしは授業で製作されたものです。



■
登った人だけが手にする、
メイド・イン・ジャパンの小さな勲章

「山バッジ」と聞いて、すぐに何のことか分かるでしょうか?山の姿などを象った、合金製の小さなバッジのこと。主に山小屋で販売されています。この山バッジ、製造を受けているのは、現在、ほんの数社しかなく、その一社が、清水澄雄さんが40年前に興した高崎金属工芸です。しかも、ほとんどが海外で製造されるなか、実はここからメイド・イン・ジャパンの山バッジが生み出されているのです。
清水さんの登山歴は18歳に始まり、70歳を超えたいまも、冬はスキー板をリュックにくくりつけ、ワシワシ雪山を登ってしまうほどの、大の山好きです。そんな清水さんの元には、山小屋のオーナーから「山と花と鳥を入れてお願い」こんな大雑把な製作依頼がくることもあるそう。けれど、迷わずひょいひょいっと図案をつくってしまうと言います。勇壮な山の姿も、小さな植物も、そこに生きる動物たちのことも「全部頭に入っているからね」と清水さん。山の魅力を知りつくす清水さんだからこそ、できることです。
清水さんが起こした図案は、彫刻、プレス、型抜きなど、日本のものづくりを支える職人さんの手から手へとリレーされ、最後に、清水さんのもとで、ひとつひとつ手作業で色をのせたり、焼き付けをするなどして完成させます。
いまは様々なものが「デザイン」される時代。もちろん、凝ったデザインの山バッジもあります。ところが、人気があるのは何故かゴツッとしたどことなく古めかしいもの。そしてそれこそが、実は清水さんのもとから生まれるメイド・イン・ジャパンの山バッジなのだそうです。印象的だったのは「デザインしちゃダメなんだよ」という清水さんの一言。自らの足で一歩ずつ登ってきた人にとって、もしかしたらバッジは自分への勲章のようなもの。素っ気ないくらい無骨なバッジだからこそ、山とのつながりを確かに感じられるのかもしれません。


写真提供:ジョウモウ大学
授業のきっかけは、息子さんの清水篤司さんが、ジョウモウ大学のスタッフに何気なく仕事のことを話したところ「えっ、山バッジ?」と驚きの反応が。そこから授業化まではあっという間だったそうです。おふたりとも「特に珍しい仕事とは思わないけどねぇ」と声を揃えますが、バッジ製作の現場なんてめったに見られるものではありません。授業に参加した学生さんたちも、このバッジ製作という珍しい「仕事」に興味を持った人たちだったといいます。
そこにいる人から見れば当たり前の景色も、外から見ればすごく面白くて魅力的な世界。地元に根付くものづくりを掘り起こし、つくり手と街の人を、授業という場が驚きという感動とともに、つないでいます。(Miki Otaka)

「ゆたり」は時の広告社の登録商標です。
(登録第5290824号)