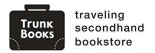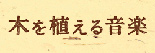野外実習~林芙美子記念館~
井上ひさしさんのお書きになった「太鼓たたいて笛ふいて」を
かんじゅく座、火曜クラスの稽古で
抜粋で練習してみようということになった。
昭和初期の女流作家、林芙美子さんの
半生を描いた物語だ。
場面のイメージを膨らませるために、
新宿は落合にある、林芙美子記念館へ
皆で足を運ぶことにしたのだ。
芝居を創るときに
稽古場に固執したくない、
どんどん外へ出て、何かをさがし、
最終的には、稽古場の中に(舞台の上に)
あるひとつの世界を作りたい、というのが
毎度毎度の狙いなのだが
ぜひ、座員の皆さんに、それを体感して欲しかった。
あらかじめ、予約を入れておいたので
新宿区のボランティアの方が
細かく解説をしてくださった。
林芙美子さんが、こだわり続けて建てた家には
そこ、かしこに工夫と趣向がみられ、
たとえ、文学に興味のない人でも、
この家には興味を持つのではないだろうか。
写真をとってもいいということだったので
庭から茶の間を撮影。

ここで、実際に、あの林芙美子女史が生活し、
なんと平成2年までご主人が暮らしていらっしゃったというのだ。
家族は、その人数、家族構成が変化すると、
それにともなって、家の内外の形も変わってゆくものだが、
ご主人は、ここを記念館になさる際、
芙美子さんが暮らしていたときの状態に、復元させた部分があるという。

屋根のデザイン、庭の竹、タンスの装飾、
さまざまなところに、工夫とこだわりが満載の家。
見学しながら、私が
「やっぱり畳がいいなあ。」
というと、
すかさず、「あら、手入れが大変なんですよ。」と、女性陣。
そこから、虫干の話、着物の洗い方、
などなど、昔の家事がいかに大変だったかという話に花が咲き
「エマさん、手水鉢(ちょうずばち)なんて知らないでしょう!」と、
楽しそうに説明してくださった。
日ごろ、「そんなこともしらないの?」と、
若手に言われていらっしゃるかもしれないが、
こういうところでは、彼らの出番だ。
日本がどん底から、はいあがるのを
すべてみて、ともに歩いてきた世代の方たちだ。
だれにきいても、古きよき時代の日本は、
うらやましく感じる。
便利さを追い求めた結果が、現在の状態だ。
後戻りは出来なくても、価値観だけは大切にしたい。
せっかくだから、集合写真。
2名お休み。

こうしてみると、男性が増えたなあ。
男性が増えると、男性だけでなく、
女性も喜ぶので、よかったよかった。
じゃあ、みなさん、稽古場で
林芙美子の茶の間を作りましょう!
~本日のありがとう~
サッカーW杯日本代表のみなさん、
今日は負けちゃったけど
勇気ある姿を魅せてくださってありがとう。
次もがんばってくださ~~い!
Trackback(0) Comments(4) by 鯨エマ|2010-06-19 22:10

- Bloger
鯨エマ
Ema Kujira
- » 最近の記事
- » カテゴリ
- » 以前の記事
- » 最近のコメント
ゆたりブログ
- 鯨エマの海千山千
Blog by 鯨エマ - 毎日をもっと楽しく、丁寧に
Blog by みきゴン - ほんのきもちです
Blog by Yamepi - まいにちが、記念日
Blog by つき - 西本淑子のボイスブログ
Blog by D.J.Yossy - お先にどうぞ
Blog by すわち - どんぐり ころころ
Blog by Masami - 子ども/アート/おもちゃ
Blog by ねもといさむ - 和紙のかわいい仲間たち
Blog by 梅原瞳渓 - アナローグ モノクロノーム
Blog by モノクロ - 滝味ブログ
Blog by 豊年万作 - ゆたりやの亭主
Blog by Yasumine - 彩り日記
Blog by ボタン - 食べるプロ
Blog by 安島夏 - 日用菓子店 冬庫
Blog by 日用菓子店 冬庫 - にわにわ
Blog by にわけん - 雨は遠いそらの上
Blog by 雨 - どうぶつごろごろ
Blog by マリサ - よかった探し
Blog by satomi - にんじん
Blog by しまじ - vege☆table
Blog by ベル - はらごしらえ記録帳
Blog by NOKKI - 一期一会的生活
Blog by スイミー - バカにつける薬
Blog by マー坊 - ゆたりろ日記
Blog by 野澤真人 - picture*book
Blog by sora - Sararaさんのさらっとな一日
Blog by Sarara - ウイリアムとオリビア
Blog by オリビア - Yum!Yum!Organic
Blog by Yummy - chuchu cafe'blog
Blog by chuchu cafe' - 農園の野菜の料理な生活
Blog by げんちゃん - kotomamiのブログ
Blog by kotomami - ガジュマル日記
Blog by 小町剛廣 - アルキニストLife
Blog by HOSSY★ - こころばかり
Blog by sabu - skyskrapa
Blog by 小手毬* - 丁寧なケ、素敵なハレ
Blog by 吉川永里子 - 音楽制作が生業
Blog by KAZU OSAWA - アレグレれんらく帳
Blog by アーリー&グレイ - okey-dokey
Blog by えだまめ - 川の生き方・僕の生き方
Blog by マーサカワマタ - ことのべ通信・電子版
Blog by ひつじ - 日本一周バイクの旅
Blog by コヤナギ - 和あらかると
Blog by 岩田晶子 - はれ時々くもり
Blog by ウタイツキ - ビューティ・レシピ
Blog by 杉浦エミ - マサヤン・スタイル
Blog by マサヤン - 手作り雑貨PULL
Blog by Katze* - もっと晴れたらいいのに
Blog by Kay - 『てぃってぃぐわ』ゆたりんちゅ
Blog by かあちゃん - こころいっぱい
Blog by なおリン - 風仁
Blog by かなめこ - 日々のはなし
Blog by まるぅ - The Journey of Life
Blog by Dan Suzuki - Others before self
Blog by 北澤杏里 - 空を歩こう
Blog by Ichi - ゆだねる
Blog by ますみ - ウルオウ*ソライロ
Blog by コムギ - チマキブログ
Blog by maki - T-shirt on Road
Blog by 北村和哉 - イロトリドリの世界
Blog by シズカメラ☆ - Fairway journal
Blog by Midori Shibayama - 研究的な生活
Blog by こいちろ - キヨ一歩
Blog by キヨ - アクトな日々
Blog by アクト農場 - chuchu
Blog by rei - おうちcafe'
Blog by roseline - イバラキイサン
Blog by grace - まんまる満月
Blog by ren - 愛娘と日常のこと
Blog by himaripapa - Kiitos
Blog by sana137 - うろこ日和。
Blog by うろ子 - pain de mie
Blog by Kanakana
「ゆたり」は時の広告社の登録商標です。
(登録第5290824号)